もっとお得に!効果が大きい節約術
「日頃からコツコツと節約しているけど、もっと固定費を削減したい!」と考える方もいるでしょう。
ここでは、長期的な目線で考えた効果をしっかりだす節約ポイントを解説します。自由度の高い戸建てならではの節約ポイントも紹介するので、参考にしてください。
効果をしっかり出す節約ポイント
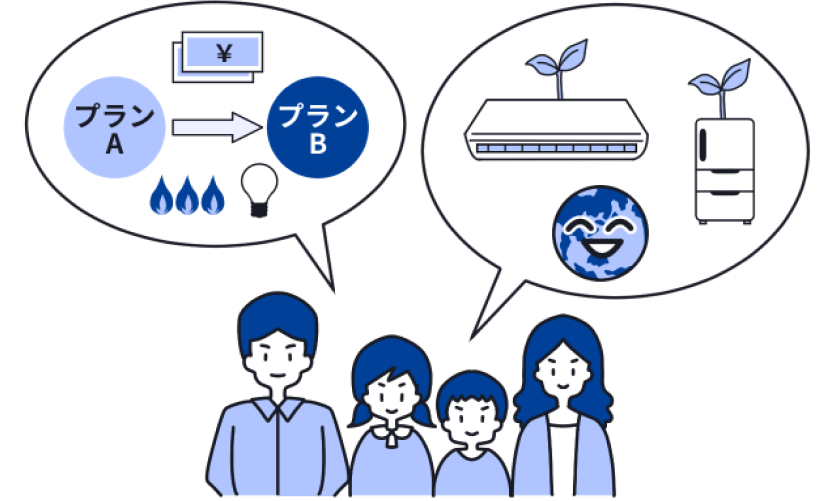
節約効果を高めるなら、契約プランの見直し、家電製品の買い替えなども選択肢になります。それぞれの節約について以下で詳しくご紹介します。
契約プランを見直す
まずは、現在契約している契約プランが最適なものであるか、見直してみましょう。
例えば、東京ガスでガスのみご契約中の方であれば、電気も東京ガスでご契約いただいたうえで「ガス・電気セット割(定額B)注1」を付帯すると、月々の電気料金注2から毎月0.5%を乗じた分が割引になります。
また、電気代はアンペア数によっても料金が変わるため、契約アンペア数を変更することでの節約も可能です。1人・2人世帯では30A、3人世帯では40A、4人世帯では50A、それ以上では60Aが大まかな目安です。
普段の生活で、家電を同時に使ったときのアンペア数を計算してみて、アンペア数にかなり余裕がある場合は、アンペア数の低い契約に変更することも検討してみましょう。
注1)適用条件を満たしている場合にお申し込みによって適用されます。
注2)電気の基本料金と電力量料金の合計額(税込)
省エネ家電(エコ家電)に買い替える
古い家電を使い続けている場合は、最新型の省エネ家電に買い替えを検討することも節約ポイントの一つです。家電を買い替えることで、大幅な電気代の節約が可能です。
10年前の製品と比較して、エアコンで約15%、冷蔵庫で約42%、温水洗浄便座で約10%、テレビで約31%の省エネが実現されています注3。
長い期間、買い替えをしていない家電製品については、省エネ家電への買い替えを検討してみることがおすすめです。
出典:環境省 デコ活「省エネ製品買換ナビゲーション
しんきゅうさん」
注3)エアコン:冷暖房兼用・壁掛け型・冷房能力2.8kWクラスの場合
冷蔵庫:定格内容積401~450Lの10年前の冷蔵庫と最新冷蔵庫の比較
温水洗浄便座:2012年の製品と2022年の製品の年間消費電力量の比較(貯湯式)・節電機能を使用した場合
テレビ:2010年の32V型液晶テレビと2020年の32V型液晶テレビの比較
なるほど。たしかに根本的な部分をきちんと見直せば、持続的な節約につながりそうですね。
「戸建て」なら節約の自由度もアップ!
持ち家の戸建てでは、自由度の高さを活かし、断熱リフォームや太陽光パネル、蓄電池の設置を実施して毎月の固定費を節約する方法もあります。
たしかに節約はしたいけれど、大掛かりなものだとかえってお金がかかってしまうのでは?
自由度の高い「戸建て」ならではの節約ポイント
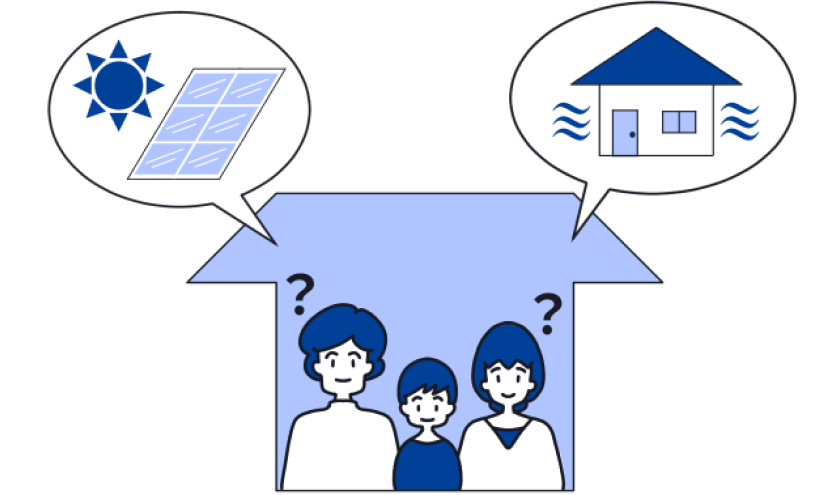
断熱リフォーム
自宅が夏は暑く、冬は寒い戸建ての場合には、断熱リフォームを実施して断熱・気密性能を高めることで解決できる可能性があります。冷暖房の効果が高まり、節電にも効果的です。
断熱リフォームの工事は、例えば以下が挙げられます。
・床・壁・屋根・天井への断熱材施工
・既存の窓の室内側に内窓を設置する
・窓ガラスを複層ガラスへ交換する
・玄関ドアを高断熱タイプのものに交換する
ぜひ省エネルギーで快適に過ごせる、住環境へのリフォームも検討してみましょう。
太陽光発電・蓄電池
電気代を大きく節約したい方は太陽光発電や蓄電池の設置を検討するのもよいでしょう。
太陽光発電は、日中の電気代を削減できるだけでなく、余った電気を売ることで収入を得ることもできます。
蓄電池は普段の生活で余った電気を貯蓄できる充電装置です。太陽光パネルが使用できない夜間の電力に活用できるため、非常時の電力としても役立ちます。
太陽光発電や蓄電池については、上級編もご覧ください。
節約だけではなく、冷暖房の効果が高まったり非常時も活躍してくれたりするのは心強いですね。
ガス・電気代の契約プランを、契約初期から変更していない方は、当時の生活スタイルと変わっていたり、新しいプランが提供されていたりする可能性もあるので、定期的に見直すことをおすすめします。
また、長期的な目線で節約を考えると、省エネ家電への買い替えや、戸建ての方はリフォームなどの大規模なてこ入れを検討することで効果が期待できます。自宅の固定費の削減に本格的に取り組みたいと考えている方は、ぜひ検討してみてください。
この記事の監修者

鶏冠井悠二
1級FP技能士・CFP・節約生活スペシャリスト・証券外務員一種・投資診断士・クレジットカードアドバイザー®
コンサルタント会社、生命保険会社を経験した後、ファイナンシャルプランナーとして独立。「資産形成を通じて便利で豊かな人生を送って頂く」ことを目指して相談・記事監修・執筆業務を手掛ける。担当分野は資産運用、保険、投資、NISAやiDeCo、仮想通貨、相続、クレジットカードやポイ活など幅広く対応。現在、WEB専門のファイナンシャルプランナーとして活動中。

節約は意識しているつもりですが、もっと効果を実感できる節約方法はありますか?